
オムニチャネル
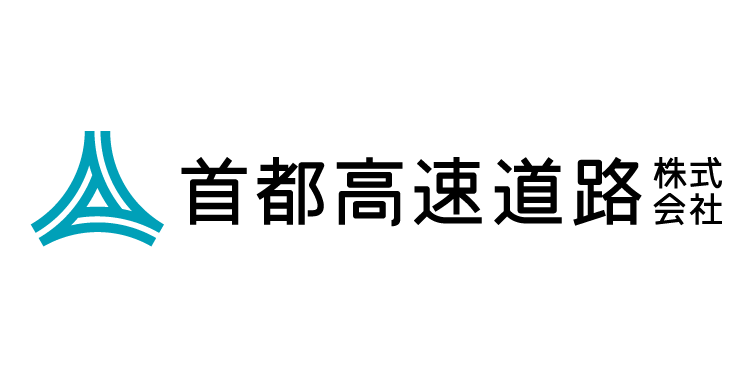
切電マニュアル×音声認識システムで現場力アップ!
安心の対応体制を構築した舞台裏とは
経営理念である「お客さま第一」を実現する、お客さまセンターの体制強化
お客さま対応を99%完結する安定したセンター運営の実現
導入サービス
(2025年7月時点)



CS・サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進企画課
課長 恩田 和典 様(写真右側)

法人ビジネス第2統括本部 ソリューション第3本部 第1営業部
部長 黒澤 裕之(写真左側)
日々、多くのお客さまが利用する首都高速道路。その安全と円滑な交通を支える上で数々の問合せに対応するお客さまセンターは、24時間365日の受付体制の構築や、エスカレートするカスハラへの対応が課題でした。ETCの普及が進む中で、お客さまとの数少ない直接の接点として機能し続け、経営理念である「お客さま第一」を実現する体制を目指すために外部委託を決定。入札の結果、2017年9月にアルティウスリンクが業務を受託。そこから7年以上にわたるパートナーシップの中で両社はいかにしてこれらの課題を乗り越えてきたか。首都高速道路でお客さまセンターを統括する恩田様と、アルティウスリンクの首都高速道路様担当の部長を務める黒澤に話を聞きました。

-当時の課題とアルティウスリンクへの業務委託の経緯を教えてください。
恩田様当時は自社でお客さまセンターを運営していましたが、24時間365日のお問合せに対応できる体制を実現するには、人員の確保やそれに伴う労務管理が大きな課題でした。 ETCの普及で料金所での対面対応が減少する中、お客さまとの数少ない直接の接点として機能し続け、当社が経営理念として掲げる「お客さま第一」の体制を実現するためには専門会社への外部委託が必要だと判断し、入札による複数社の比較検討の結果、アルティウスリンクに業務を委託することとなりました。
委託当初は運営上いくつかの課題に直面しましたが、アルティウスリンクとの連携によりひとつずつ解決し、おかげさまで現在の24時間365日の安定稼働に至っております。人員規模と、それにともなう複雑なシフト管理や多様な勤務形態での労務管理を考えると、あらためてアルティウスリンクにお願いして良かったと感じております。
-運営していく中で、他に課題となった点を教えてください。
恩田様課題としては大きく2つ。「非常時の人員体制」と、「カスハラへの対策」です。非常時の体制というのは、東京オリンピック・パラリンピックなどの大型イベント、台風や大雪といったある程度予測できる対応にとどまらない、地震のような予測不能な非常事態への対応です。
もうひとつの課題は、カスハラへの対応です。なかには長年にわたり苦情を繰り返すお客さまと最終的に訴訟にまで発展するケースもありました。こうした件を経て、「会社としてどうやってカスハラから社員を守るか」については、当社内での大きな課題となりました。
-その2つの課題をどのように解決したのでしょうか。
恩田様非常時の体制を考える大きなきっかけとなったのが、2021年10月7日夜に、都内で震度5強を観測した地震です。夜間帯でオペレーター配置が少ない状況で問合せ数が急増し、応答率が大幅に低下しました。この地震をきっかけに、予測困難な事態にも柔軟に対応できる方法がないか、アルティウスリンクと検討を始めた次第です。
首都高速道路では、業務継続計画(BCP)の一環として、震度5強以上の地震が発生した場合には、勤務時間外であっても近隣に居住する社員が速やかに参集する体制を整えています。この「非常参集体制」をアルティウスリンクのオペレーターにもお願いできないかといった協力を仰ぎ、体制を整えていったというわけです。
黒澤非常時に備えた人員体制の構築は難易度の高い取り組みでしたが、アルティウスリンクにはこれまで電気や通信といったライフライン関連業務の実績があり、非常時でも事業を継続しながら、オペレーターが安全に出勤できるための仕組みを構築・実践してきた知見があります。今回はその経験を活かし、公共交通機関が止まった際も、代替手段で出勤可能な人員をあらかじめリストアップして備えることで、非常事態発生時にも安定した運営を保てる体制を構築しました。
恩田様もうひとつの課題のカスハラ対策として、「切電マニュアル(カスハラ対策マニュアル)」を策定しました。このマニュアルのポイントは、30分以上同じ内容を繰り返し主張、不当な要求、暴言などが発生した場合には、オペレーターが自らの判断で「電話を切っても良い」という明確なルールを定めたことです。これは「お客さまからの電話はこちらから切るべきではない」という従来の考え方を覆すもので、専門家の意見と裁判での経験を活かし、策定に至りました。このマニュアルでの運用をサポートしているのが、黒澤様からご提案いただいた音声認識システムAmiVoiceです。
黒澤AmiVoiceはお客さまとの会話を自動でテキスト化するシステムです。この導入により、電話対応中のリアルタイムでのアラート表示や会話履歴の確認が可能となり、スーパーバイザーがオペレーターをその場で的確にサポートできるようになりました。会話中に問題が発生した場合、保留にして状況を説明・相談する必要はありません。スーパーバイザーはAmiVoiceで履歴をさかのぼることで状況を把握できるため、すぐにフォローに入ることができます。また、切電マニュアルを実行する上でも、オペレーターの判断が客観的に記録・保管されるので、マニュアルの遵守状況も正しく検証できるようになりました。こういった支援体制があることで、オペレーターからも「電話に出ることへの恐怖心がなくなり、より丁寧な対応をしようと前向きな気持ちになれた」「何かあっても会社に守ってもらえる安心感は大きい」という声をもらっています。
恩田様カスハラ対策開始後、約2年間でこのマニュアルに則った対応が34件発生※していますが、後を引くトラブルには発展しておらず、オペレーターが自信を持って対応できる体制となっています。
恩田様首都高速道路では、お客さまセンターの社内における位置付けも変わってきています。かつては「お客さまの声をただ取り次ぐだけの部署」と見られがちだったお客さまセンターが、こういったカスハラへの対応や社内向けの見学会を経て、今では社員が本来業務に集中できるよう99%のお客さま対応をクローズする「防波堤」として認識され始めてきました。こういった認知が広まった背景には、アルティウスリンクのオペレーターが発揮する専門性と、ホスピタリティある対応が大きく貢献しています。例えば目的地までの所要時間の問合せでは、単に時間を伝えるだけでなく、「目的地までは20分ですが、この先500mに落下物がありますのでご注意ください」といった、ナビには表示されない、お客さまの立場に立った追加情報の提供などは、社内見学会でもそのお客さまを大切にする姿勢に驚かれるほどです。
こうした社内でのお客さまセンター業務の重要度が高まった結果、2025年4月より、お客さまセンターはグループ会社である「首都高アソシエイト株式会社」を介した契約形態に移行しました。これはノウハウを社内に蓄積すると共に、今後の安定的な運営を確保し、密接なパートナーシップを築ける体制とすることを目的にしています。その新体制のなか、今後は単に電話を受けるだけでなく、AmiVoiceで分析したお客さまからの問合せデータを、事業や施策に活かす取り組みにも注力していく考えです。これは私たち単独では成し得ない挑戦ですから、これからもアルティウスリンクと二人三脚で、お客さま第一という理念に沿ったサービスを提供し続けていきたいと考えています。

首都高速道路株式会社は、日本の首都圏における交通インフラを支える企業です。高速道路の建設、管理、運営を主な事業とし、円滑な交通と地域の発展に貢献しています。経営理念として「お客さま第一」を掲げ、カーボンニュートラル戦略やDX推進、カスハラ対策など、持続可能で安全な道路サービスの提供に取り組んでいます。

オムニチャネル

コンタクトセンター

レポート

コンタクトセンター