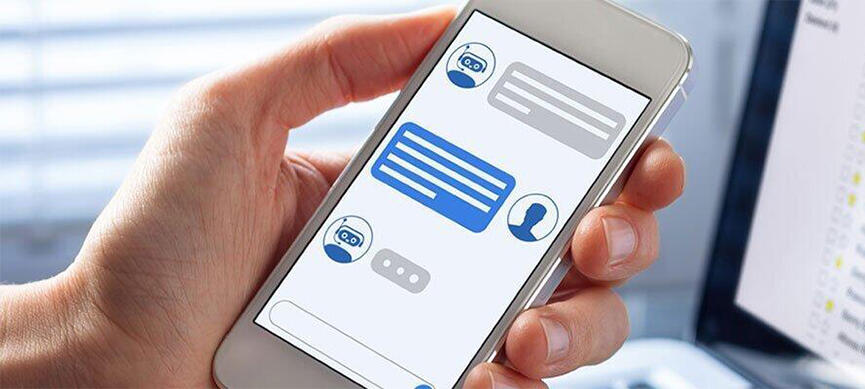チャットボットを新たな顧客接点のチャネルとして導入する企業が増える中、成果を出している企業がある一方、導入したものの思うように使いこなせず持て余している事例も出てきています。その明暗を分ける要因にはいったい何があるのでしょうか?導入に際しては、自社の経営方針に沿った業務課題を事前に検討しておく必要があります。ここを押さえられていないと、導入が目的化したプロジェクトとなり、効果的に使いこなせず失敗に終わってしまう可能性が高くなります。
チャットボット導入時に起こしやすい失敗要因とその対策について、以下で具体的に解説します。
失敗要因1:導入目的が定義されていない
チャットボットに限らずツールやソリューションを導入する際には、導入目的を事前に定義しておくことが必要です。 チャットボット導入時には複数の部署からメンバーが参画し、プロジェクトチームが編成されるケースがほとんどです。 目的が不明確な状態で導入を進めても、導入プロセスの中で発生する判断のタイミングごとにブレが生じます。 事前に導入目的を明確に定め、プロジェクトメンバーが同じゴールを見据えられる状態にしておくことが重要です。
チャットボットの導入目的としては、主に3つ挙げられます。
- 顧客対応の自動化による工数削減(コスト削減)
カスタマーサポートの一部をチャットボットに任せ、お客様の自己解決率を改善するものです。オペレーターリソースの工数削減の期待から、コスト削減までを見据え導入を検討する企業が多く見受けられます。また、昨今の人手不足の影響もあり、ES向上を目的として導入されるケースもあります。 - コンバージョンの改善
Web上の離脱が起きやすい場所やタイミングで、お客様の疑問を解消し、コンバージョンを上げることを期待効果として導入されています。ECサイトなどの購買行動を伴うサイトで導入が進められています。 - デジタルでの新たな顧客体験の提供
スマホファーストの時代において、どの企業でもデジタルトランスフォーメーション(DX)は重点的課題になっています。Web上での顧客接点の増加を目的として導入が検討されます。
失敗要因2:ナレッジの整備が不十分
チャットボットに組み込むナレッジの質と量は、チャットボットの効果発揮に大きな影響を与えます。チャットボットは自力で学習するものではなく、ヒトによる学習やチューニングが不可欠です。子どもに物事を教えるように、情報を与えるだけではなく、間違った答えを出してしまう場合には、正しい答えを教えていく必要があります。 ナレッジの整備は、チャットボットリリース前はもちろん、リリース後も安定稼働のため実施しなければなりません。その際に重要になるのは、顧客視点での整備ができているかどうか。実際にお客様が何に対してどんな質問をしてくるのかを見極める必要がありますが、そこにコンタクトセンターで蓄積されるお客様の声や入電の原因であるコンタクトリーズンが活用できます。お客様から直接入る生の声であり、常に最新のデータが入手できるため、質・量ともに優れたデータと言えるでしょう。このコンタクトリーズンから具体的なナレッジを作っていくことをおすすめします。
また、ナレッジの整備をするための体制も整えておく必要があります。PDCAサイクルを自社でしっかり回せるのかを見極め、もしリソースや知見が不足しているようであれば、アウトソースし専門のノウハウの力を借り滞りなくサイクルを回すこともひとつの手段です。ナレッジの整備が不十分なチャットボットはお客様の不満の種となり得ます。
失敗要因3:他のチャネルとの連携がない
スマホファースト時代において、チャットボットは新たな顧客体験を提供できるチャネルです。しかし、チャットボットだけですべてのお客様の問題を解決することはできません。起きている問題や疑問によっては、ヒトによるサポートを求められることもあり、またお客様によってもその時々のシチュエーションによって求めるチャネルは変わってくるでしょう。
例えば、チャットボットで解決できずオペレーターと直接話したいと思った場合、チャットボットでの対応を一度切断し、電話をかけなおす必要があります。しかしながら、この場合の多くは電話で再度チャットボット上でのやりとり内容を伝えなければならず、お客様には手間と負担をかけてしまいます。 このような状況を回避するためには、チャネルごとの対応領域を定め、問合せの内容に応じて適切なチャネルに誘導する必要があります。ヒトでなくても対応できる簡易な問合せはチャットボット、過去の問合せ履歴と紐づくような複雑な問合せは有人チャネル(電話、有人チャットなど)へ。それぞれの対応範囲を見極める際にも、コンタクトリーズンは有効です。
また、チャットボットの対応履歴を自動的に有人チャネルにシームレスに連携できるようになると、さらによりよい顧客体験を提供できるようになり、企業への信頼度も向上するでしょう。
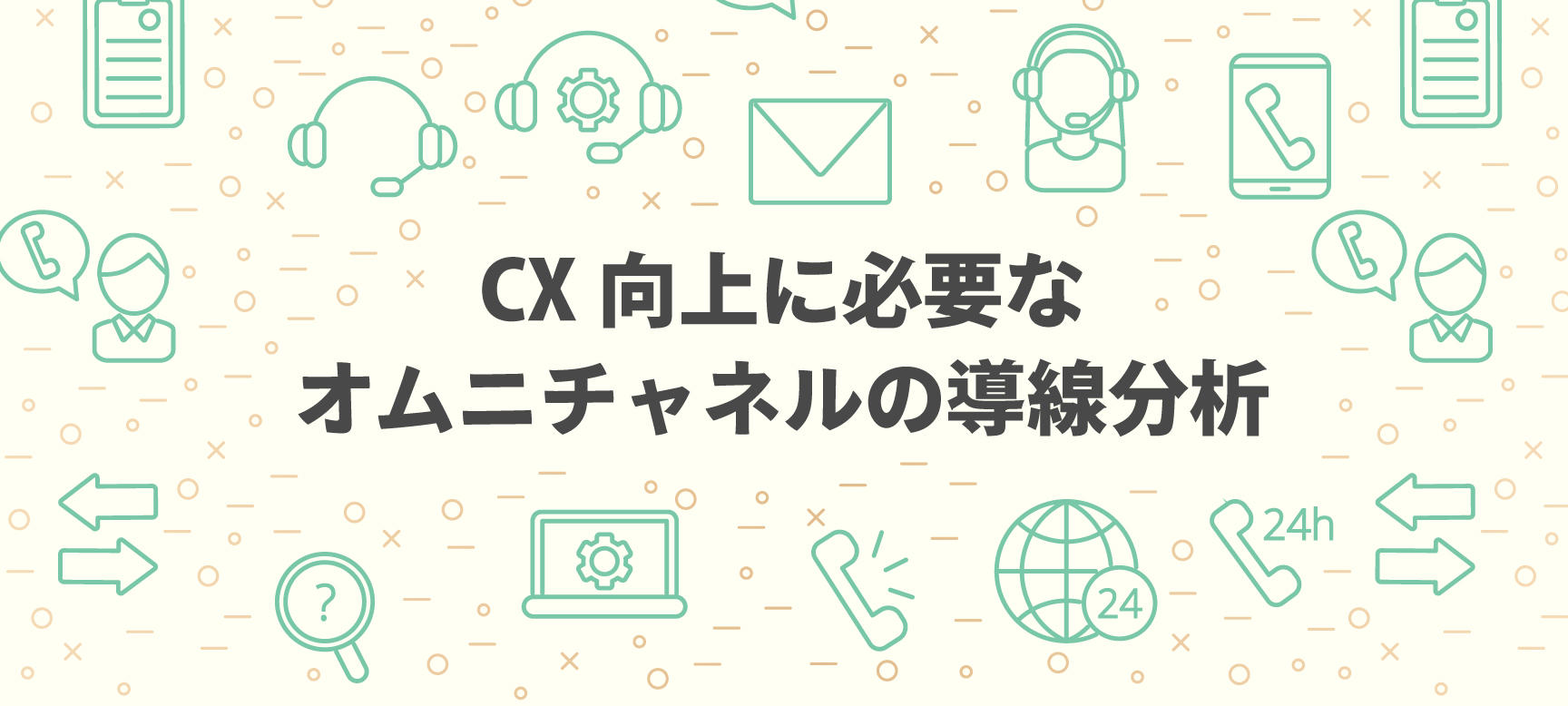
CX向上に必要なオムニチャネルの導線分析
コラム
自社に適したチャネルの選定とそのチャネルの効果を最大化するため方法について解説いたします。
アルティウスリンクができること
コンタクトセンター運営で得たコンタクトリーズン分析のノウハウは、FAQの整備やチャットボットの構築、運用にすぐ活用することができます。コンタクトリーズンを起点として、お客様の求めるFAQの作成や、最適な回答が可能なチャットボットを構築。さらにWebアクセス解析により顧客行動を可視化することで、それらを最適な場所に設置でき、効果を最大化させることが可能です。当社グループ会社が提供するチャットボット「Virtual Agent®」の導入はもちろん、チャットボットの要件定義~構築~運用までをフルパッケージでご提供し、業務課題の解決をサポートいたします。
各企業の経営方針や業務課題に寄り添い、導入をご支援いたしますので、お気軽にお問合せください。