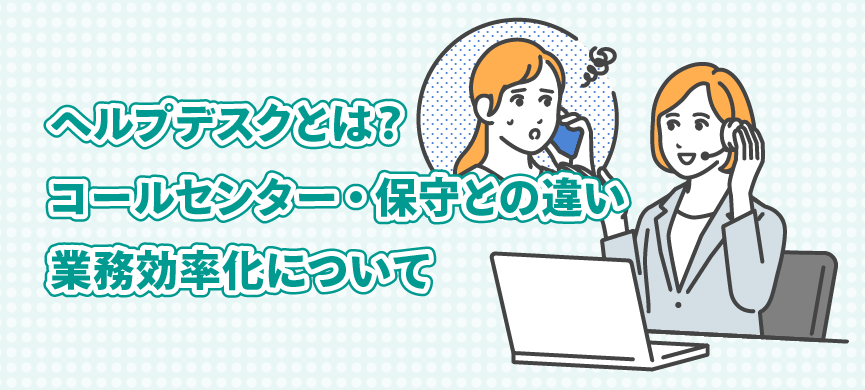「オムニチャネル」とは、企業とお客様の接点となるチャネルを連携させ、お客様にアプローチするマーケティング戦略のことです。カスタマーエクスペリエンス(以下、CX)の向上、顧客接点の増加を目的として、多くの企業が導入を進めています。
なんとなく分かっているけど、他人に説明できるほど深く理解はできていない。
そんな方に向け、今回はオムニチャネルの基礎知識と導入効果を最大化するヒントをお伝えします。
オムニチャネルとは?
「オムニチャネル」とは、企業とお客様の接点となるチャネルを連携させ、お客様にアプローチを図るマーケティング戦略のことです。
具体的には次のような例が挙げられます。
「テレビCMで気になる商品を見つけた。ネットで調べると、商品を販売するメーカーのECサイトにたどり着く。ECサイトで購入手続きを進めていると、サイト上でおすすめ商品を紹介され、その場で追加購入。翌日、近くのコンビニで受け取った。」
ここでは「テレビCM」「ECサイト」「コンビニ」3つのチャネルが連携されています。
もしECサイトを設けておらず、コンビニでの受け取りも実施していなければ、お客様はネットでの商品検索のみにとどまっていたかもしれません。
複数のチャネルで顧客接点を持ち、連携させた情報を活用してお客様にアプローチをする。
これらのプロセスを経て販売促進につなげるのがオムニチャネルの特徴です。
チャネルは他にも、アプリやSNSなど多岐にわたります。
複数のチャネルを連携させることで、どのチャネルからもスムーズに購入できるようになり、これまでにない新しい顧客体験を実現します。
よく間違えられる「マルチチャネル」「O2O」との違い
オムニチャネルと混同されやすいのが「マルチチャネル」と「O2O」です。それぞれの戦略や考え方の違いをみていきましょう。
「マルチチャネル」とは、複数のチャネルを提供する戦略です。
例えば、実店舗で販売、ECサイトでの販売などを単体チャネルで提供するのではなく、「実店舗を運営しながら、ECサイトでも販売を行う」といった戦略です。
主なチャネルの種類
|
|
主なチャネルの種類
- 実店舗
- ECサイト
- 企業ホームページ
- 電話
- 訪問販売
- メール
- FAX
- テレビ通販
- カタログ通販
- SNS
- チラシ、パンフレット
一見オムニチャネルと違いがないように捉えられますが、オムニチャネルはチャネル同士の連携がされているに対し、マルチチャネルは連携がなく、個々のチャネルが単独で運営されているという違いがあります。
それゆえ、実店舗とECサイトで在庫管理が別だったり、顧客データが共有されていなかったりするため、お客様の消費行動が途切れやすく、機会損失につながりかねないのが懸念点です。
複数チャネルの設置により顧客接点は増えますが、オムニチャネルと比較するとお客様を購入まで導くには弱いでしょう。
「O2O」は「Online to Offline」の略です。
その名の通り「オンラインからオフラインへ」お客様を誘導する戦略です。
スマートフォンアプリ上で、店舗で使える新商品のクーポンなどを発行し店舗への来店を促すといった施策に使われます。
スマートフォンアプリ、店舗と複数のチャネルは利用していますが、お客様へのアプローチがオンラインからオフラインと一方通行にとどまる点が、オムニチャネルとの違いです。
そのため、実店舗が自宅から遠いお客様や、オンラインサービスの利用頻度が低いシニア層をターゲットにする場合は不向きな手法といえるでしょう。
オムニチャネルを活用するメリット
では具体的にオムニチャネルを活用するメリットについて、みてみましょう。
顧客接点の増加
ひとつが「顧客接点の増加」です。
多種多様なチャネルにはそれぞれ、強みがあります。
例えば、SNSは若年層によく利用され、お昼のテレビ販売は主婦やシニア層向けなど。
チャネルの特徴を把握して設置することで、より幅広い層の顧客接点を持つことができます。
さらにオムニチャネルによってひとりのお客様に対する接点量を増やすことも可能です。
アプリ・SNS・Web広告など、複数のチャネル連携によって購買の機会増加に貢献しています。
また各チャネルの顧客情報や商品在庫管理を連携し一元管理することで、アップセルやクロスセルの機会損失防止の効果も見込めるでしょう。
CXの向上
Webをはじめ24時間365日対応できるチャネルと営業時間内に人が対応する電話や実店舗チャネルとの連携は、CX向上につながります。
今まで電話や実店舗だけの窓口だった企業では、平日フルタイムで働く世代が接点を持ちづらいことが課題でした。
ところがスマートフォンの普及により、いつでも、どこでもアクセスすることができ、必要であれば電話や実店舗もあわせて利用するなど、一人ひとりのライフスタイルや問合わせ内容に合わせた顧客接点を持つことができるようになりました。
消費者は好きなチャネルを選べるため、時間制限や利用チャネルの制限による問合せのストレスが減少し、結果としてCX向上につながるのです。
上記2つのメリットによる「お客様の中長期的な囲い込み」
顧客接点の増加と、CXの向上が成されれば、中長期的なお客様の囲い込みが実現可能です。
仮に一時的に利用したお客様でも、オムニチャネルのシームレスな購買体験に価値を感じ、何度もリピートして自社サービスを利用するようになれば、結果として顧客ロイヤルティの高い顧客層が増えていく構造ができあがります。
これらは中長期的にオムニチャネルを導入するからこそ得られるメリットです。
継続的に運用可能な環境を整えることで、導入効果を何倍にも高められる可能性もあるでしょう。
オムニチャネルの効果を最大化する「戦略」とは?
期待効果の高いオムニチャネルですが、その効果を最大化させるためには、どのような戦略をたてれば良いのでしょうか。
社内でデータを連携させる
オムニチャネルを導入する前に、各チャネルそれぞれで管理していた在庫管理や顧客データなどの情報を一元管理し、運用できる社内環境を整えることが必要です。
とはいえ、企業によっては一筋縄ではいかないこともあるでしょう。
有効な手段のひとつが「組織編成」です。
チャネル運用を、部署を分けて行っている場合は、部署を横断して統括する人材を配置。
さらにオムニチャネルとして共通の売上目標を立てることも有効です。各部署が一枚岩になりオムニチャネルの成功に向け取り組む理由づけが生まれます。わかりやすい目標があれば必要なプロセスも明確になり、協力的に働きかけてくれる人が増えるでしょう。
お客様のニーズを捉える
オムニチャネルは単にチャネルの数を増やし、連携させればいいということではありません。
オムニチャネルの目的は、あくまでCX向上です。
適切なオムニチャネル化を目指すには、まずお客様のニーズを把握する必要があります。
方法は主に2つ。
Web解析ツールの使用と、お客様の生の声を聞くことです。Web解析ツールには「Google Search Console」「Googleアナリティクス」「Googleキーワードプランナー」などがあります。
これらを活用することで、お客様がWebチャネルにアクセスした時間帯やよく検索されるキーワードを把握することができます。
お客様の生の声では 「口コミサイト」 「お問合せ内容」 「Webアンケート調査」 「座談会の開催」などを活用すると効果的です。
対話をすることで小さなニーズを引き出せ、お客様が感じているベネフィットや改善点を直に吸収できる貴重な機会となります。
どちらも偏りなく使いこなすことで、より正確なお客様のニーズが洗い出せます。
オムニチャネルを導入する前に、迷ったら「オムニチャネル診断」
スマートフォンやWebが主流な時代背景を踏まえ、オムニチャネルを導入する企業は増えています。
とはいえ、実際にどのチャネルをどのように導入すべきなのかわからないといったご相談を受けることが多いのも実情です。
そこで当社は、オムニチャネル戦略を実現するにあたっての課題抽出を行う「オムニチャネル診断」サービスをご用意しています。
大手通信事業者様では、漠然とオムニチャネル化を推進していましたが、本サービスにより有人対応と自動化対応の切り分けが明確になり、「販売機会の増加」と「自動化」を両立させた戦略を立案することに成功しています。
データに基づいた見解により、お客様企業と当社が同じ課題認識・ゴールを見据えた状態でオムニチャネル化に向けてのスタートを切ることができています。
顧客ニーズが多様化している今、顧客接点のデジタルチャネルを含むオムニチャネル化は避けては通れないでしょう。
しかしそのために必要なのはお客様のニーズを可視化し、自社のお客様に適したオムニチャネル戦略を立案することです。
「オムニチャネル診断」サービスでは、オムニチャネルを成功させるための設計図としてお客様企業をサポートします。