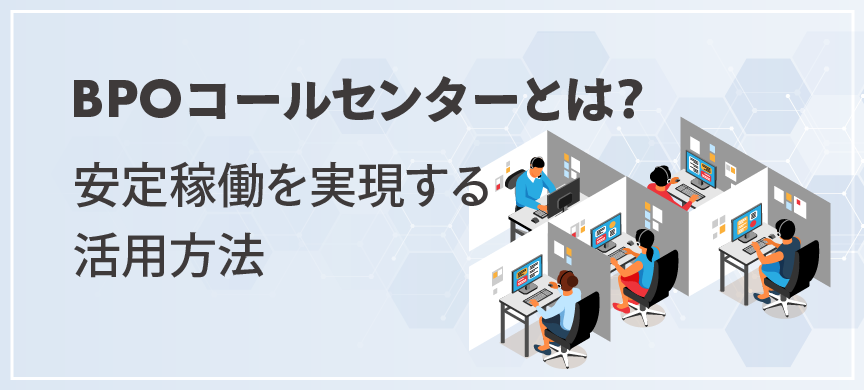コンタクトセンターを在宅勤務化する際の「問題」
コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフトを検討する際には、まずその「問題点」をしっかりと把握する必要があります。
そこで、特に多くの企業が懸念する「コンタクトセンター在宅勤務化の問題点」について見ていきましょう。
在宅コンタクトセンターはうまくいかないのか?
そもそも論として、「在宅コンタクトセンターはうまくいかない」と考える企業が少なくありません。
2021年にリックテレコム社が実施した「コンタクトセンター実態調査」によると、「情報セキュリティ」に関する項目が「在宅運営の課題」、そして「在宅勤務制度を導入しない理由」それぞれのトップとなりました。実際コンタクトセンターの在宅勤務化においてセキュリティ対策は重要課題であり、それを運営上の課題、もしくは導入しない理由として挙げる企業が数多くなっています。
またオペレーターとのコミュニケーション問題や、オペレーターとのコミュニケーション問題なども、「在宅勤務化の障壁」となっていることが明らかとなりました。
しかしこれらの問題点は、基本的に「既存のセンターの環境を、そのまま自宅に持っていく」という発想でスタートしているところから生まれています。既存のセンター環境を自宅に再現しようとすれば、セキュリティに不安が生じるのは当然ですし、オペレーターとうまくコミュニケーションが取れないケースも出てきてしまいます。
つまり、「在宅コンタクトセンターはうまくいかない」という問題は、在宅コンタクトセンター導入をメインに据えてアクションを考えていることが原因となることが多いのです。
コンタクトセンターは在宅勤務にマッチしないのか?
さらに、直近のコロナ禍をはじめとするパンデミックや自然災害時に業務継続するための対応、いわゆる「BCP対策」という観点からも、在宅勤務化はうまくいかないと考える企業が少なくありません。有事の際にオペレーターの自宅で業務が遂行できるという保証はなく、費用対効果の点で思ったような効果が得られない可能性もあるからです。
実際コロナ禍が収まった2025年現在、在宅勤務化からオフィス回帰する企業が増えています。
しかし、だからといって「コンタクトセンターの在宅勤務化」の廃止は、今後の2030年問題、さらにはCX/DXの潮流からもリスクの高い選択とも言えます。
2030年問題・CX向上手段としての「在宅勤務化/デジタルシフト」
「2030年問題」とは、少子高齢化と人口減少により、2030年に生産年齢人口の不足が深刻化すると予測される社会問題の総称です。
2030年問題では、「労働力不足によるサービスレベルの低下」や「人材不足による倒産」など、企業が将来にわたって事業を継続するうえで深刻な問題をもたらすと予想されています。現在でも人材不足が叫ばれるコンタクトセンター業への影響は言うまでもなく、労働力の確保と同時に生産性の向上が欠かせません。
さらに、近年のCX/DXの潮流は、各企業のサービス提供による顧客体験の飛躍的な進歩につながっています。そのため、現行のコンタクトセンターを踏襲するだけではお客様はその品質に満足できず、今後は衰退していくだけとなる恐れがあるのです。
コンタクトセンターは現在、「2030年問題」と「CX/DXの潮流」という2つの脅威にさらされています。この脅威を乗り越えるため、コンタクトセンターには「労働形態の多様化による労働力の囲い込み」と、「お客様接点の高度化・多様化によるお客様(エンドユーザー)の囲い込み」が求められています。
このための手段として、「コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト」が存在するのです。
「在宅勤務」は労働人口減への打ち手になり得るか?
あるいは、「在宅勤務化は本当に労働人口減への打ち手になり得るか?」という疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、2024年にアルティウスリンクが「在宅コンタクトセンター」と「通常のコンタクトセンター(非在宅)」の応募倍率を比較してみたところ、「在宅コンタクトセンター」は「非在宅」の約3倍の応募がきていることが確認されました。
さらに特徴的なのが、「デジタルに親和性が高い」と想定される若年層の応募比率が高いという点です。今後の労働力を確保するうえで、若年層の応募比率が重要であることは明らかです。
「家でも働ける」、「遠方でも働ける」という選択肢が存在することが、採用における大きな武器になり得ることは十分想定されます。
2つの脅威に直面するコンタクトセンターの「対策」
「2030年問題」と「CX/DXの潮流」という2つの脅威に対し、個別に対策案を実行していくのは得策ではありません。
実際、最近ではコンタクトセンター業務に関わるさまざまなソリューションが登場していますが、「導入してみたものの、思ったような効果が出ていない」「そもそも効果があったかどうかわからない」といったケースが多々見られます。
個別の課題に対し、個別のソリューションを順次、建て増し的に導入してしまうと、コンタクトセンター全体の業務効率化において十分な効果が発揮されないばかりか、場合によってはお客様にとって「改悪」となってしまうケースも考えられます。
「2030年問題」と「CX/DXの潮流」という2つの脅威に対抗するには、コンタクトセンターのあり方そのもの「再構築」することが重要となります。お客様に提供すべき機能を改めて整理し、コンタクトセンターのあり方を再構築することが、遠回りに見えて実は近道となるのです。
コンタクトセンターを「再構築」する筋道(STPDサイクル)
- See:現状把握
- Think:コンセプトを描く
- Plan:コンセプトの計画化
- Do:計画の実行
コンタクトセンターを「再構築」する方法はさまざまありますが、今回は「STPD」のフレームを元に検討する方法をご紹介します。
「STPD」とは、「See」「Think」「Plan」「Do」という4つのアクションを使って「正確な現状把握」と「目指す姿のコンセプト化」、「コンセプトの計画化」「計画の実行」を進めるフレームワークです。
「STPD」で特に重要なのが、「See」と「Think」です。この2つが不十分だと、「やることが目的」化してしまい、コンタクトセンターの再構築がうまくいかないケースが往々にして発生します。そのため今回は「See」と「Think」を中心にお話していきます。
コンタクトセンターを再構築するための「See」
コンタクトセンターを再構築するための「See」(正しい現状把握)では、お客様視点を中心に、現状を正しくとらえることが重要です。
具体的には、「お客様が期待していること」「お客様の問合せ導線」「企業側のサポート導線」という3つの軸に対し、「コンタクトリーズン」「カスタマージャーニー」「タッチポイント」「サポートプロセス」「サポート体制」という5つのアプローチで現状把握を進めます。
まずは「コンタクトリーズン」によって、お客様がセンターに寄せる疑問・要望・トラブルなどの具体的な内容を把握します。そして、「カスタマージャーニー」と「お客様とのタッチポイント」により、お客様にどのようなサポートを提供できているか、そしてそのサポート機能にお客様はどのようにしてたどり着くかを可視化します。
さらに、「サポートプロセス」と「サポート体制」によって、お客様の問合せ解消に対して、現行どのようなプロセスと役割を用意しているかを明らかにします。
この5つのアプローチによる現状把握(See)が完了したら、次のステップとしてコンセプトワーク(Think)を行っていきます。
コンタクトセンターを再構築するための「Think」
Thinkでは主に「お客様に対してどんなサービスを提供すべきか」という観点から、コンタクトリーズンレベルで改めて見直し、在宅勤務化・デジタルシフトを含め、サポート体制を抜本的に改革するコンセプトを描いていきます。
例えば、現行の体制で「すべてのお客様対応時に本人確認を行う」という運用を行っている場合、オペレーターはお客様情報を閲覧するため、セキュリティレベルはどうしても高く保つ必要があります。
しかし、「本当にすべての問合せで本人確認が必要なのか」「お客様にとってそれは望ましいアクションなのか」という観点から、「本人確認はしなくても回答可能な問合せ」が多いのであれば、その対応業務はセキュリティリスクが下がり、在宅勤務化の可能性が生まれます。
こういった「現行のサポート体制を改革するコンセプト」を描くことで初めて、「労働人口確保のための在宅勤務化」や「AIチャットボットによるデジタルシフト」というソリューション導入のロジックを立てることができます。
「既存の体制に合わせたコンセプト」ではなく、「既存のサポート体制を抜本的に改革するコンセプト」を描くこと。それがコンタクトのセンターの「再構築」における「Think」で重要となるのです。
SeeとThinkで見えてくる在宅勤務化/デジタルシフト
「See」で収集した情報群から、お客様にとっての「ペインとゲイン」、つまり、悪い影響と良い影響をもたらすものを分析します。そしてお客様の期待やエフォート(ネガティブに感じること)とコンフォート(ポジティブに感じること)が定義すれば、「Think」で「何を提供すべきか」ということが見えきます。
提供すべき機能や提供すべき価値・体験などをコンセプトとして描ければ、その対応策としての「コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト」も見えてくるはずです。
【成功事例.1】コンタクトセンターのデジタルシフト
それでは実際に「STPD」のフレームワークによる「コンタクトセンターのデジタルシフト」の成功事例をご紹介します。
鉄道事業者様より、スマホアプリサポートセンター運用における「コスト構造改革」「オペレーションのデジタル化」「お客様接点のマルチチャネル化」についてのご相談を受けたアルティウスリンクでは、「サービス利用からサポートまでスマホ操作で完結するサービス」というコンセプトとプランをご提案。
結果、それまで10%台だった問合せの「ノンボイス比率」を80%超まで向上。つまり問合せのうち80%がメール、チャット、Webフォームといったテキストコミュニケーションで完結させることに成功いたしました。
またこの事例ではWebフォームを使った申請処理が抜群の効果を発揮し、それまで平均通話時間が10分程度だったところが、わずか1分で処理が完結。生産性も劇的に向上しました。
この事例では、アルティウスリンク側でまずコンタクトリーズンを収集し、既存のFAQ等のコンテンツと突合しました。これにより、お客様の自己解決率に向上の余地があることを確認できました。
その上で、「スマホアプリによるサポートセンター」という特性を生かすため、「スマホ操作で完結するサービス」というコンセプトを立て、コンタクトリーズンごとに「どのチャネルで解決すべきか」を仕分けていきました。
これにより、必要なチャネルと各チャネルの役割・カバー範囲を明確化。チャネルの新設と既存チャネルの精度向上、お客様を適切なチャネルへ導く導線設計、さらに導線の周知活動にも力を入れました。
【成功事例.2】コンタクトセンターの在宅勤務化
続いて「コンタクトセンターの在宅勤務化」の成功事例をご紹介します。
飲料サプライヤ様より、既存コンタクトセンターの「完全在宅勤務化」についてご相談を受けたアルティウスリンクでは、管理者・オペレーターも全員が在宅勤務で成立する「オフィスを持たない次世代センター」を構築。完全在宅勤務化により従業員の満足度が向上し、さらに在宅勤務運用下でよく耳にする「パフォーマンス低下」を起こさない事例となりました。
完全在宅勤務化に向け、アルティウスリンクでは「既存業務の完全可視化」からスタートしました。管理者やオペレーターが、朝出勤してから退勤まで、一日の流れに沿って一挙手一投足レベルでリスト化することで、業務を細かく仕分けしていきました。
仕分けの軸としたのは、「何がその行動の起点となっているか」「どんな媒体で実施するタスクか」「コミュニケーションは発生するか」等です。特に、管理者の業務は目視による気付きが多く、これを在宅勤務下においてどのようにキャッチするかが重要課題となりました。
その上で、既存業務を踏襲するのではなく、「在宅勤務」という条件下に適した業務構成に組み替えるというコンセプトを描き、そのコンセプトを実現するプロセスや体制の組み換えを行いました。そしてそのプロセスをまずは仮想在宅下で検証。プロセスの精度向上だけでなく、仮想在宅における従業員の業務練度も向上することで、スムーズな在宅移行が可能になりました。
その結果、コンタクトセンターのパフォーマンスは在宅勤務化後も落ちることなく維持され、同業務を実施している他社のスコアを大きく凌駕することに成功しました。さらに「従業員満足度アンケート」では在宅勤務前よりも在宅勤務後で満足度が向上。業務品質を落とさず、従業員にも歓迎される取り組みとなりました。
コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト対策まとめ
「コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト」を成功に導くには、「問題を正しく把握する」こと、そして「対策の筋道を立てる」という2点が重要となります。
コンタクトセンターが直面する「労働人口の減少」や「CX/DXの潮流」という問題。この問題の対策として、既存の体制を維持するのではなく、コンタクトセンターの再構築が求められています。その再構築の手段として、「コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト」に活路が見いだせます。
そしてコンタクトセンターを再構築する際には、「STPD」のフレームにならい、お客様目線での情報収集(See)と、収集した情報からコンセプト考案(Think)を十分に行ったうえで、具体的な計画化と実行に移すことが大切です。
「コンタクトセンターの在宅勤務化/デジタルシフト」を目的化するのではなく、問題を改善するためにやりたいこと、目指したい姿を明確にしたうえで、この先を見据えたコンタクトセンターの形を再構築する。そしてその手段として在宅勤務化/デジタルシフトを検討することが、コンタクトセンターの2030年問題とCX向上の対策となるのです。
アルティウスリンクの在宅勤務化/デジタルシフト支援
国内最大規模のコンタクトセンター運用実績を誇るアルティウスリンクでは、在宅勤務化/デジタルシフトを支援する「コンサルティング&アナリティクスサービス」をご用意しております。
コンタクトセンター/バックオフィスセンターの構築・運用ノウハウを基に、お客様企業のセンター運用の現状を把握・評価したうえで数値化。品質向上、業務最適化に向けた課題を明らかにし、成長ステージに合わせたコンサルティングを実施することで最適なコミュニケーションを提供し、顧客体験(CX)の創造を実現いたします。
また「コンサルティング&アナリティクスサービス」以外にも、BPOサービスとしての「コンサルティング&アナリティクスサービス」や「バックオフィスサービス」など、幅広いソリューションもご用意しております。
在宅勤務化/デジタルシフトをはじめとする、コンタクトセンターの再構築・業務改善を検討される際には、ぜひアルティウスリンクまでご相談ください。